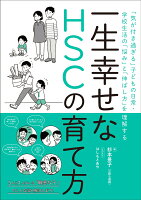そんな悩みに『一生幸せなHSCの育て方』はお答えしています。
※HSPを知らない方は、こちらの記事を読んでいただくと本記事が理解しやすくなるので、合わせて読んでみてください。

・STEP1 HSCを理解する
・STEP2 HSCにとっての学校生活を理解する
・STEP3 HSCを伸ばす関わり方を知る
・STEP4 日常生活の悩みを解決する(子どもへの働きかけ)
・STEP5 学校生活の悩みを解決する(学校・先生への働きかけ)
上記の内容から
本書を読むことで、繊細な子(HSC)の長所の伸ばし方や日常生活で抱える問題を解決することができます。
・HSCが抱える日常や学校生活での悩みの原因を学びたい人
・悩みに対する具体的な解決方法を知りたい人
・HSCとの関わり方を見つけたい保護者や先生
こういった人に本書はおすすめです。
それではいきましょう。
※楽天やAmazonでは他の方のレビューもご覧になれます↓
目次
『一生幸せなHSCの育て方』について
著者:杉本景子さん

・公認心理師、看護師、保護司
・NPO法人千葉こども家庭支援センター理事長
・千葉市スクールメディカルサポート・コーディネーター
また、NPO法人千葉こども家庭支援センターでは実際に杉本さん自身がHSCに関するカウンセリングも行っています。
気になった方はぜひそちらもチェックしてみてくださいね。
⇒NPO法人千葉こども家庭支援センター
本書の特徴
特徴は主に3つあります。
特徴①:専門的知見からHSCを理解できる
特徴②:日常生活での実際の悩みやそれに対する関わり方が学べる
特徴③:悩みに対する具体的な解決策が見つかる
特徴①:専門的知見からHSCを理解できる
STEP1では、公認心理師である著者の専門的知見から、HSCについてわかりやすく学ぶことができます。
✓そもそもHSCってなに?
✓HSCと非HSCでは、同じ「刺激」でも受け取り方は違う!
✓HSCは敏感さを活かして素晴らしい人生を送れる!
上記のように基礎知識だけでなく、HSCがとても素敵な気質であることを理解することができます。
特徴②:日常生活での実際の悩みやそれに対する関わり方が学べる
STEP2とSTEP3では、HSCの子が生活の中で実際に抱える悩みと、大人がその悩み対して、どのように関わればよいのかを知ることができます。
✓HSCにとって学校は「未知との遭遇」そのもの!
✓HSCにとっての「学校生活・行事」とは?
✓HSCを伸ばすためのマインドセット(心構え)
✓話の聞き方 など
このように、生活の中でも過ごす時間の長い「学校での悩み」が中心です。
また、大人の関わり方としては、子どもの欠点を改善するのではなく、良い部分の伸ばし方が理解できる内容となっています。
特徴③:悩みに対する具体的な解決策が見つかる
残りのSTEP4とSTEP5では、具体的な事例から日常や学校生活での悩みに関する解決策を提示してくれています。
✓引っ込み思案すぎる
✓遊び仲間に振り回される
✓学校にHSCであることを伝える・伝えないで悩む
✓怒鳴る先生がいて怖い など
こういった事例が全部で27ケースとたくさんあります。
そして、上記の事例は
①子どもへの働きかけのケース
②学校・先生への働きかけのケース
このように、当事者(HSCの子)の視点やそれを取り巻く環境からの様々なアプローチがあります。
このことから、きっと自分に合った解決策が見つかるはずです。
『一生幸せなHSCの育て方』の学びポイント3選

学びポイント①:HSCと非HSCでも相性がいい場合があります
「HSC(繊細な子)」と「非HSC(繊細ではない子)」
上記2人は気が合わないのではないか?と思う人もいるかもしれません。
しかし本書では、実は相性がいい場合もあると言っています。
理由としては、繊細な気質に違いがあっても価値観が似ているパターンもあるからです。
では、どのような価値観だと相性がいいのか。
本書では以下のように言っています。
私はこれまで人の気質について考察してきましたが、むしろ、敏感ではない人たちの中にも、HSPやHSCと非常に相性のよい人たちがいるということに気づきました。その代表は、おおらかなタイプ、正義感が強いタイプ、社会貢献思考のタイプの人たちです。
このような人たちは、細やかさという点ではHSPやHSCにはかなわない一方で、HSPやHSCが慎重になって行動に移せないことを、いとも簡単にぱっと実行することができます。それが例え失敗に終わったとしても、敏感な人たちがまたじっくり考察することで、よりよい方法を編み出していくこともできます。
上記をまとめると
【相性のいいタイプ】
①おおらか②正義感が強い③社会貢献思考
【物事を進める際の役割】
◎非HSC⇒物事を前に進めるエンジンになる
◎HSC⇒じっくり考えながら細やかに調整する
このようになります。
つまり、「考え方の傾向」と「持っている強み」に着目すると、HSCと非HSCでもよりよい関係性が構築できるということです。
「繊細か繊細ではないか」という二極端で考えてしまっている人は、ぜひ違った視点から見てみましょう。
学びポイント②:HSCにとってクラスメイトはどんな存在?
子どもにとって学校は多くの時間を費やす生活場面です。その中で、よく関わるのが学校のクラスメイト。その人間関係は、HSCにとって様々なストレスを抱える傾向があります。
そんなクラスメイトたちをHSCはどのように捉え、
そしてクラスメイトからはどのように思われているのか、本書では解説してくれています。
具体的には以下のような項目についてです。
①誰かが泣いていると自分のことのように苦しいです
②人の不調や気持ちにもつられます
③困っている子を助けられないと絶望します
④八方美人に見られてしまうことがあります
⑤「いけないんだー」という子は謎の存在です
⑥誘いを断るのが苦手です
⑦自分の意見を譲らない人に好かれます
⑧気の合う子と少数で遊ぶのはとても楽しいです
⑨自分が興味をもつ話をするときには目を輝かせよく話します
このように9項目あり、様々な苦労や困難があります。
ただ、読んでわかる通り⑧や⑨のようにプラス面も存在するため、辛いことだけではありません。
実際にプラス面については、以下のように本書で言っています。
⑧気の合う子と少数で遊ぶのはとても楽しいです
HSPに子ども時代のことを聞くと、落ち着いた雰囲気で気の合う穏やかな友達とごっこ遊びや工作、読者を黙々とできたときはとても幸せだったと言います。
⑨自分が興味をもつ話をするときには目を輝かせよく話します
慎重に発言するHSCですが、自分の興味・関心のあることについて話す機会が与えられる、もしくは、話ができる友達がいると、うそのように生き生き話しはじめることがあります。物事を深く考えるHSCにとって、共感してもらえたり知ろうとしてもらえたりしたときの喜びはとても大きいのです。
引用からもわかるように、HSCはクラスメイトと関わること自体が苦痛なわけではありません。HSCと気の合う人は、学びポイント①でも話した通り必ず存在します。
親御さんは上記の特徴を把握した上で、HSCの子ならではの悩みをしっかり受け止めてあげましょう。
学びポイント③:怒鳴る先生がいて怖い
学校ではクラスメイト以外にも、深く関わる人がいます。
それは先生です。
そして先生にもいろいろなタイプがいますが、HSCは「怒鳴る先生」をとても苦手としています。
なぜならHSCの子は、怒鳴る先生が近くにいるだけで恐怖を感じ、力を発揮できなくなるからです。
ではこのような場合、どう対応したらいいのか。
結論、子どもが悩んでいるなら、親はすぐに学校へ相談するべきであると本書では言っています。
私は、教育において、怒鳴るという行為は必要ないと考えます。先生に限らず、親が怒鳴るのも、また、怒鳴ることを周りが容認する行為もダメです。怒鳴ると多くの子どもは一瞬大人に従いますが、その実何も学んでいないからです。
HSCは5人に1人の割合でいます。ですので、学校にはほかにも怖がっている子どもが少なからずいるはずです。不登校につながる場合もあるので、このケースは学校に相談するべきです。
また学校に相談する場合は、相談相手も状況に応じて見極める必要があります。
(深刻な場合⇒校長先生、教頭先生など / 少し気になる程度⇒身近な先生、スクールカウンセラーなど)
もし子どもから「怒鳴る先生が怖い」という訴えがあったら、深刻な問題になる前にすぐに適切な対応をとってあげましょう。
『一生幸せなHSCの育て方』のまとめ
『一生幸せなHSCの育て方』のポイントについてここで、再度まとめておきます。
学びポイント①:HSCと非HSCでも相性がいい場合があります
HSCは①おおらか②正義感が強い③社会貢献思考のタイプの非HSCとは相性がいい
学びポイント②:HSCにとってクラスメイトはどんな存在?
クラスメイトとの人間関係にストレスを溜めやすい傾向がある。しかし、気の合う子と少数で落ち着いて遊ぶことは好む
学びポイント③:怒鳴る先生がいて怖い
HSCの子から怒鳴る先生が怖いという訴えがあれば、親はすぐに学校へ相談する
実際の本書には、ここでは紹介しきれなかったすばらしい内容が盛りだくさんです!気になった方はぜひ読んでみてください。
きっとHSCの子が自分の良さに気づき幸せに生活できるようになるはずです!
今回は以上です。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
※楽天やAmazonでは他の方のレビューもご覧になれます↓